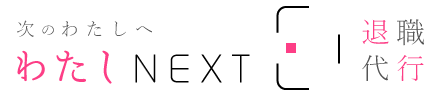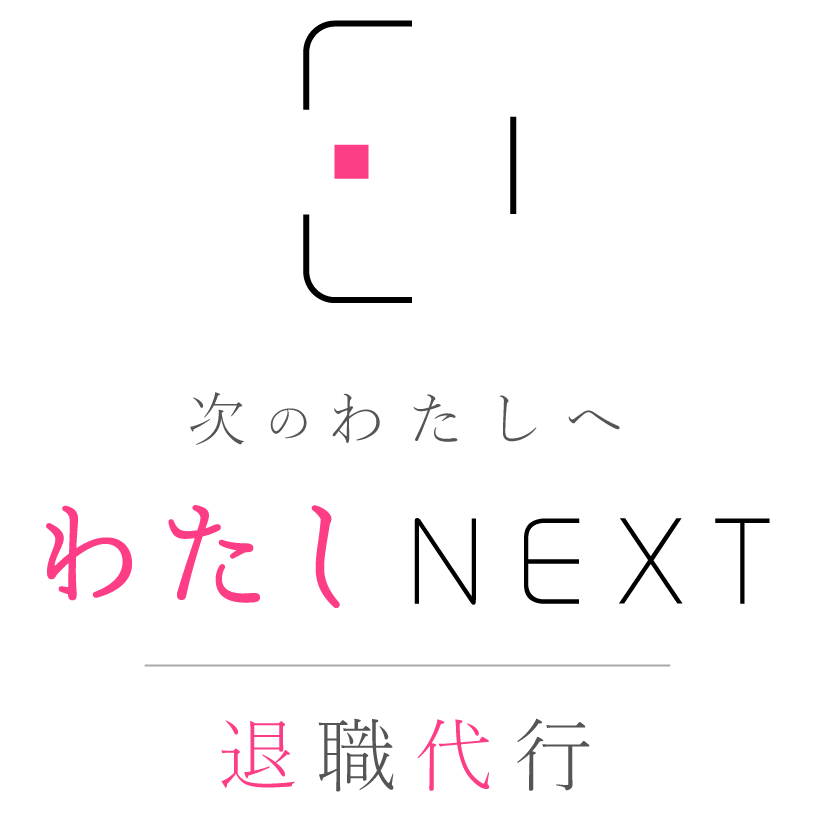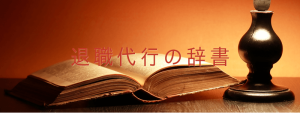社宅・寮住みも退職代行は使える?退去日・費用・注意点までとことん解説

社宅や寮に住んでいる人も、退職代行サービスを利用することはもちろん可能です。
今回は、社宅や寮に住んでいる人が知っておくべき情報として、借り上げ社宅と社有社宅の違いなどをはじめとした社宅や寮に関する基礎知識、社宅や寮に住んでいる人が退職代行サービスを利用した場合の退去日までの流れ、おすすめの退職代行サービス事業者、社宅や寮に住む人が退職代行サービスを利用する際の注意点や節約ポイントについて紹介していきます。
現在社宅や寮に住んでいることで退職代行サービスを使えるかどうか不安になっている人はもちろん、退職代行サービスを利用した際に損をしたくないという人もぜひチェックしてみてください。
目次
結論:社宅や寮住みの人も退職代行で辞められる!
結論からいうと、社宅や寮に住んでいても退職代行サービスを利用して会社を辞めることは可能です。
社宅や寮が会社の持ち物であることを理由に退職を引き止められてしまうのではないかと懸念している人もいるかもしれませんが、雇用期間に定めのない労働者には、法律で退職の自由が認められています。
そのため、仮に社宅や寮に住んでいるとしても退職代行サービスを利用して会社を辞めることに全く問題はありません。
これは、借り上げ社宅や社有社宅など、どのような賃貸契約になっていても同じです。
下記ではまず、社宅や寮の違い、借り上げ社宅と社有社宅の意味について解説していきますので、自分の住んでいる社宅や寮がどれに該当するのかを確認してみましょう。
社宅や寮の違いとは?
よく聞く「借り上げ社宅」って何?
社宅や寮は一括りにされることが多いですが、実は社宅や寮にも種類があることをご存じでしょうか?
まず社宅について説明すると、社宅は下記の2種類に分けることができます。現在主流になっているのは借り上げ社宅で、聞いたことがあるという人もいるかもしれません。
・借り上げ住宅:借り上げ社宅の場合、所有者は管理会社またはオーナーで、会社が賃貸契約を結んで社員へ貸し出す社宅のことを指します。個別に契約するため、立地や間取りなど社員の希望が通りやすい点が借り上げ社宅のポイントともいえます。
・社有社宅:社有社宅の場合、所有者は会社となり、会社から社員へ貸し出す社宅のことを指します。そもそも会社が所有している物件となりますので、社員が立地や間取りなどを選ぶことはできません。
また、借り上げ社宅や社有社宅のように寮にも種類があり、下記の2つに分けられます。
・独身寮:配偶者や子どもがいない人が住むことができる寮。
・単身赴任寮:結婚している、または子どもがいる人が出張や単身赴任先で利用することができる寮。
「社有社宅だから」「借り上げ社宅だから」という理由で退職代行サービスの利用に何か不具合が生じるということは全くありませんが、基礎知識として覚えておくと良いでしょう。
【状況別】社宅や寮の退去日はいつ?当てはまったら猶予期間アリ!?

冒頭では、社宅や寮に住んでいたとしても退職代行サービスを利用して退職することはもちろん可能であることをお伝えしました。
例外は認められないため、「借り上げ社宅に住んでいるから」など社宅や寮の種類を理由に退職代行サービスの利用ができないということもありません。
上記について確認できたら、社宅や寮に住んでいて退職代行サービスの利用を検討している人が次に気になるのは、退去日についてではないでしょうか。
一般的にいえば退職日が退去日として扱われていることが多いですが、退去日に関する規定は会社によって異なっており一概には言えないため、あらかじめ社内規定を確認し、退去日に関してどのような記載があるかをチェックしておく必要があります。
ただし、これから紹介する条件に当てはまっている人は、退去日までの期間に猶予が生まれます。知らずにいると会社側がその事実を無視して退職手続きを進めてしまうことも考えられますので、まずは下記の条件に自分が当てはまっているかどうかを確認してみてください。
有給休暇が残っている場合
社員が有給休暇の取得を希望した場合、会社側は基本的にそれを拒否することができません。それは、退職時も同様です。
そのため、これまでに付与された有給休暇が残っている人は、残っている有給休暇の日数がそのまま退去日までの猶予期間となります。
▶退職代行でも有給消化して退職可能!拒否られても対応できる事業者は?
ただし、ブラック企業に勤めている場合には、会社側が嫌がらせとして有給休暇の取得を拒否してくることも考えられます。
このような場合、退職代行サービスから有給消化できるように交渉してほしい、という要望が生まれるのが自然かと思いますが、ここで注意が必要なのは、有給休暇の取得に関する交渉ができるのは退職代行サービスの中でも労働組合か弁護士が運営している退職代行サービスに限られる、という点です。
そもそも退職代行サービスは運営元の違いによって大きく3種類に分けることができ、それぞれ労働組合、弁護士、民間企業運営となっていますが、退職に関する交渉ができるのは弁護士と労働組合が運営元になっている退職代行サービスのみです。
万が一、民間企業が運営する退職代行サービスが会社へ何らかの交渉を行った場合、非弁行為(違法行為)として処罰の対象になることもあります。
周辺相場と同程度の家賃を支払っている場合
社宅や寮に住んでいるとしても、周辺の賃貸物件の相場と同等の家賃を支払っている人であれば、一般的な賃貸住宅と同じ法律が適用されます。
その場合は、家賃を滞納したなどの正当な理由がない限り、会社側が強制的に退去を命じることはできません。
そして、たとえ正当な理由があったとしても退去日の半年前までに通告する必要があるため、退去日までに最低でも半年間の猶予がある、ということになります。
借り上げ社宅+大家さんと交渉できる場合
社宅や寮の種類については冒頭で紹介していますが、現在借り上げ社宅に住んでいる人で、大家さんと直接賃貸契約を結ぶことができた場合には借り上げ社宅から退去する必要はなく、そのまま住み続けることができます。
一方で、賃貸契約は借り上げ社宅として結んでいたものを継続するのではなく新たに結び直すことになるため、借り上げ社宅として住んでいたところへ継続して住む場合であっても敷金礼金などの支払いが必要になるという点には注意が必要です。
退職代行を使って社宅や寮を退去する流れはコレ!
上記では、社宅や寮に住んでいても退職代行サービスを利用できることや借り上げ社宅と社有社宅の違いを含めた社宅や寮の基礎知識、退去日に猶予が生まれる条件についてお伝えしてきました。
ここでは、退職代行サービスを利用した場合、どのような流れで社宅や寮の退去日を迎えるのか、その流れについて解説していきます。
まず、退去日までの流れを簡単に箇条書きにすると下記のようになっています。
②退職代行サービスへの依頼と料金支払い
③退職先の情報と退職に関する要望を伝える
④希望日に退職代行を実施
⑤貸与品や私物の返却・回収
⑥退去日までに退去を完了する
それぞれの工程については下記で説明していますので、具体的なイメージを掴みたいという人は確認してみてください。
①退職代行サービスへ無料相談
まずは、退職代行サービスに依頼する前段階として、無料相談で現在の状況や退職に関する要望を退職代行サービス事業者へ伝えましょう。
この段階で不明点をクリアにして、自分の要望にも対応してくれる退職代行サービスかどうかを判断することによって、依頼後に齟齬が生まれる可能性がなくなります。
また、無料相談を通して、対応の丁寧さやスピード感などを複数社比較してみるのもよいでしょう。
②退職代行サービスへの依頼と料金支払い
依頼先の退職代行サービスを決めたら、正式に依頼して依頼金額を支払います。
このとき、依頼金額が料金相場の範疇かどうか、最終確認しておくことをおすすめします。
▶退職代行とは?流れと初めて退職代行を使う人が必ず知るべき7つ
③退職先の情報と退職に関する要望を伝える
依頼したあとは、退職する会社の連絡先や担当者名などの情報を伝えることはもちろん、あらためて退職に関する要望も伝えます。
これ以降、会社との直接的な連絡は退職代行サービスが行うことになるため、退職希望者が自分で会社へ連絡する必要はありません。
④希望日に退職代行を実施
退職代行サービスへ希望日程を伝えると、その日に退職代行を実施します。
その際、有給消化を希望する場合には、その旨を伝えるとともに有給消化を考慮した上で設定した退職希望日も伝えます。
有給休暇の残日数については事前に確認できるとスムーズですが、自分で確認することが難しいということも少なくないでしょう。
その場合には、退職代行を実施した際に退職代行サービス事業者から確認することももちろん可能です。
⑤貸与品や私物の返却・回収
退職代行サービス事業者から退職意思を伝えたあとは、会社から入社時に貸与されたものを郵送で返却し、会社に置いたままになっている私物があれば、それらを郵送で送ってもらうよう、退職代行サービス事業者が会社へ手配します。
ただし、この場合の送料については退職希望者が負担することになります。
社宅や寮に住んでいる人の場合、退去費用や入居費用などがかさむことが考えられるため、少しでも退職に関わる費用を抑えたいのであれば、出勤している間に返却や回収を済ませておくことをおすすめします。
⑥退去日までに退去を完了する
上記のすべてを完了させた後は退去日までに引っ越し準備を行い、退去を完了させます。
社宅や寮住みで退職代行を使うときの注意点とは

社宅や寮に住んでいる場合で退職代行サービスを利用できること、退去日までに猶予期間が生まれる条件、退職代行サービスを利用する場合の退去日までの流れについてはこれまで紹介してきたとおりです。
ここからは、社宅や寮住みの人には特に知っておいていただきたい、退職代行サービスを利用する際の注意点について紹介していきます。退去日までの流れをよりスムーズにするためのポイントでもありますので、退職代行サービスに依頼する前段階でぜひ確認しておいてください。
労働組合または弁護士運営の退職代行へ依頼する
繰り返しにはなってしまいますが、有給休暇の消化や退去日など、退職にあたって会社へ何らかの交渉をしたい場合には、労働組合または弁護士運営の退職代行サービスでなければ対応ができません。
万が一民間企業運営の退職代行サービスが交渉を行い非弁行為と判断されてしまった場合、直接的に退職希望者へ被害が及ぶことはほぼありませんが、事情聴取などで間接的に時間を取られてしまう可能性があります。
余計なストレスや不安が増えてしまう原因にもなりますので、退去日など何かしらの交渉が必要になる可能性があるケースでは、労働組合または弁護士運営の退職代行サービスへ依頼しておけば安心です。
退去時の立ち会いは任意のため拒否も可能。もし立ち会うなら家族や知り合いと一緒に行く
社宅や寮に住んでいる場合、退去時の立ち会いが必須なのではと心配になっている人がいるかもしれませんが、結論からいえば立ち会いは任意のため、拒否しても問題はありません。
ただし、立ち会いではどの程度の修繕が必要かを判断することになるため、確認しておきたいという人もいるかもしれません。
その場合には、家族や信頼できる知り合いと一緒に立ち会うことをおすすめします。
立ち会い当日に同じ社宅や寮に住んでいる上司や同僚に会う可能性はゼロではないため、一人で立ち会うのではなく、誰かと一緒に行くことで嫌な思いをしなくて済むでしょう。
私物はできるだけ持ち帰っておく
退去日までの流れでも少し触れていますが、会社に残っている私物がある場合には、出勤している間にできるだけ持ち帰っておくことをおすすめします。
会社に私物を残したまま退職代行を実施した場合、即日退職によりそれ以降出勤する必要がなくなるため、私物を回収する方法は郵送のみになります。
そうなると引っ越し先の住所を知られてしまうことになるため、「嫌がらせされるのでは」など退職希望者側が余計な不安を抱いてしまう可能性もあります。
会社に残っている私物の中でどうしても回収したいものがある場合には、実家の住所宛てに送ってもらうというのも一つの手ですが、最善策は出勤している間にすべて持ち帰っておくことだといえます。
社宅や寮住みの退職代行が得意!経験豊富な退職代行サービス2選
ここからは、これまで紹介してきた内容を踏まえた上で、社宅や寮に住んでいる人が退職する際の対応にも慣れている、実績の多い退職代行サービス事業者を2つ紹介していきます。
わたしNEXT<女性の退職代行>

「わたしNEXT<女性の退職代行>」は、業界団体である日本退職代行協会による厳正な審査を通過し、信頼できる退職代行サービスにのみ与えられる「特級認定」を取得している労働組合運営の退職代行サービスです。
アルバイト・パートは18,800円(税込)、正社員は21,800円(税込)と低価格に設定されていることに加えて、後払いやコンビニ支払いを含む様々な支払い方法の中から退職希望者が自由に選択できるため、残業終わりや深夜であっても支払いを完了させることができることはもちろん、手持ちはないけど今すぐ退職したいという人でも好きなタイミングで依頼が可能です。
また、創業から20年以上退職代行サービスを専門に行っている退職代行サービスであり、社宅や寮に住んでいる人の退職に関する経験も豊富であるため、安心して依頼が可能です。
| サービス名 | 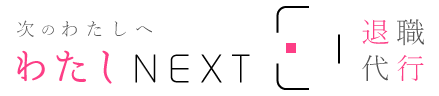 |
| ホームページ | わたしNEXT<女性の退職代行> |
| 対応時間 | ◎
(24時間365日) |
| 退職成功率 | 100% |
| 24時間対応 | ◎
(無料相談できる!) |
| JRAA認定 | 特級認定(最高クラス) |
| 運営 | 労働組合 |
| 依頼金額 | アルバイト・パート ¥18,800(税込)
正社員 ¥21,800(税込) |
| 支払い方法 | 銀行振込、翌月後払い、コンビニ後払い、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード(LINE PAY、au PAY、dカードプリペイド等)、ペイパル、コンビニ決済、楽天ペイ、PayPay(ペイペイ)、キャリア決済(ドコモ払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い) |
男の退職代行
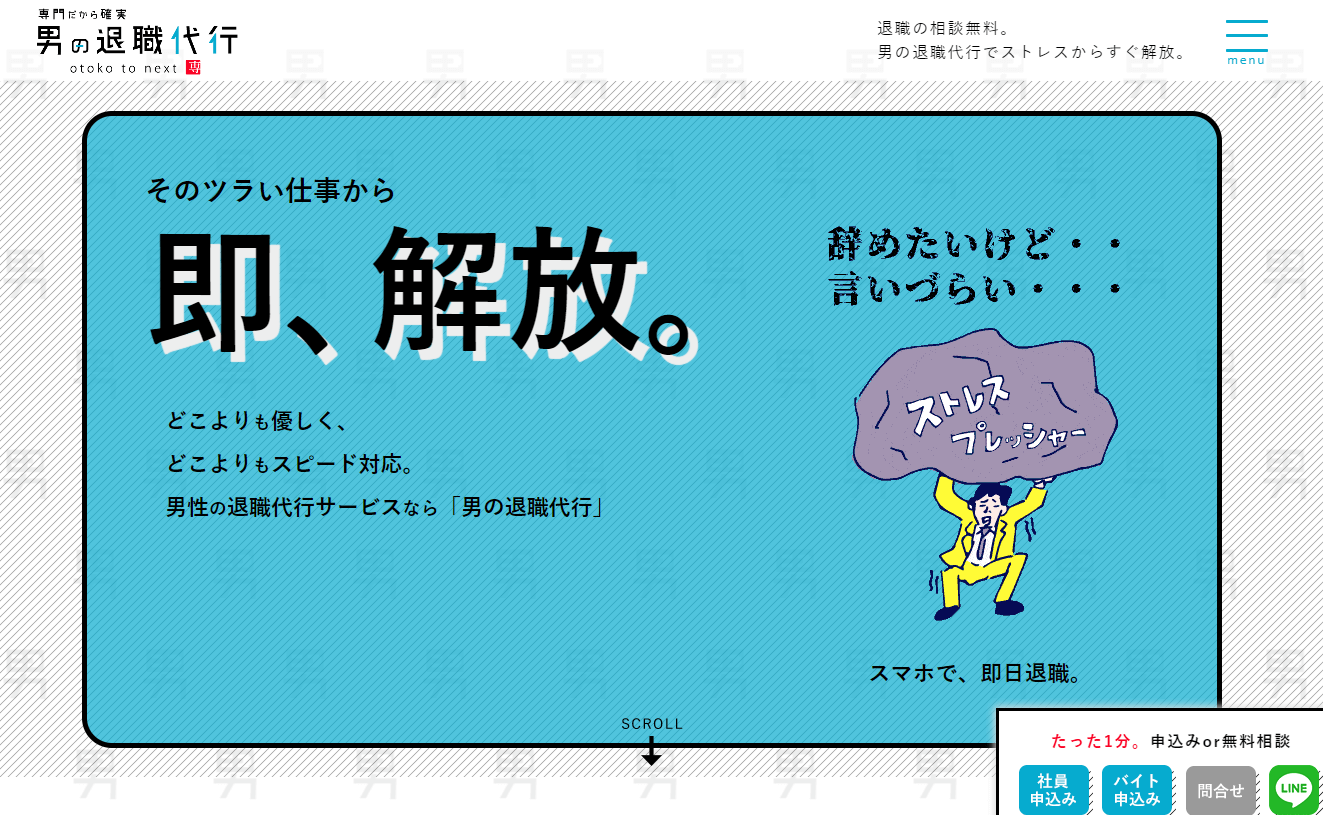
「男の退職代行」は、実績数は5万件を超えている退職代行サービスであり、社宅や寮に住んでいる人の退職に関する対応にも慣れているため、退職失敗やトラブルになるリスクを回避したいという人から人気を集めています。
また、労働組合が運営元となっているため、団体交渉権を行使して有給消化や未払い賃金などについても正当に交渉することができ、違法性がない安心の退職代行サービスでもあります。
依頼金額はアルバイト・パートが18,800円(税込)、正社員が21,800円(税込)となっていて、労働組合運営としては最安値ともいえる価格帯でありながら、退職に関しては弁護士と同様の幅広い対応が可能であるため、男性を中心に利用者が増加し続けています。
社宅や寮に住んでいる場合、ただでさえ通常よりも退職時の費用がかさんでしまうことが予想されるため、コスパ良く退職したいという人にこそおすすめしたい退職代行サービスです。
| サービス名 |  |
| ホームページ | 男の退職代行 |
| 対応時間 | ◎
(24時間365日) |
| 退職成功率 | 100% |
| 24時間対応 | ◎
(無料相談できる!) |
| JRAA認定 | 特級認定(最高クラス) |
| 運営 | 労働組合 |
| 依頼金額 | アルバイト・パート ¥18,800(税込)
正社員 ¥21,800(税込) |
| 支払い方法 | 銀行振込、翌月後払い、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード(LINE PAY、au PAY、dカードプリペイド等)、ペイパル、コンビニ決済、楽天ペイ、PayPay(ペイペイ)、キャリア決済(ドコモ払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い) |
社宅や寮の退去っていくら?とにかく節約したい人の注意点
ここまでは、社宅や寮に住む人でも退職代行サービスを利用できること、社宅や寮に住む人が退職代行サービスを利用する際の基礎知識や注意点について紹介してきました。
ここからは、社宅や寮の退去に伴いどのような費用が発生するのかを紹介するとともに、できる限り費用を節約するためにはどのような方法があるのかも併せて解説していきます。
①引っ越し費用
引っ越し業者に依頼する場合には、引っ越し業者への依頼費用も発生します。
引っ越し業者の繁忙期は2月下旬から4月上旬となっていて、この時期に依頼してしまうと値段が高騰してしまうため、もし可能であれば退職時期が引っ越し業者の繁忙期と被らないようにすると引っ越し費用を抑えることができます。
また、現在借り上げ社宅に住んでいて、新たに賃貸契約を結び直して借り上げ社宅として住んでいた家に継続して住み続ける場合には引っ越し費用はかかりません。
②引っ越し先の初期費用
社宅や寮を退去する場合、必ず必要になるのが引っ越し先の初期費用です。
できる限り初期費用を節約したいという場合には、敷金や礼金をできるだけ安く抑えられる物件を探すことはもちろん、退去日までの間に社宅や寮を完備している会社へ転職するというのも手です。
さらに、借り上げ社宅に住んでいて退職後もそのまま住み続けるというケースでは、大家さんとの関係性にもよりますが初期費用に関する相談を直接することができるかもしれません。
③社宅や寮の修繕費用(ある場合)
社宅や寮の修繕費用は、必ず発生するわけではありません。
備え付けの家具や床、壁紙などを汚さないように普段から気を付けておけば、余計な修繕費用を取られる心配はありません。
社宅・寮住みも退職代行は使える?退去日・費用・注意点までとことん解説、まとめ
冒頭では、社宅や寮に住んでいる人も退職代行サービスを利用することは可能であること、借り上げ社宅や社有社宅をはじめとした社宅や寮の種類、退去日までに猶予期間が生まれる条件、退職代行サービスへ依頼した場合の退去日までの流れについて紹介しました。
これらは、退職代行サービスへ依頼する前に知っておくべき基礎知識ともいえます。
そして、中盤から後半にかけては、社宅や寮住みの人が退職代行サービスを利用する際の注意点、社宅や寮住みの場合でもおすすめの退職代行サービス2選、とにかく節約したい人に向けた注意点について紹介してきました。
社宅や寮に住んでいる人の場合であっても退職代行サービスを利用できることはもちろんですが、社宅や寮に住んでいる人はほとんどが退職時に引っ越しを伴うことになるため、費用を抑えるためにはいくつかの注意点があります。
また、引っ越し準備も併せて行うことになるため、退去日に関する交渉が可能な労働組合または弁護士が運営している退職代行サービスを利用することをおすすめします。
社宅や寮に住んでいる皆さんがストレスなくスムーズに退職するために、本記事が少しでも役立つことを祈っています。
「退職代行サービス」の利用について
「わたしNEXT<女性の退職代行>」「男の退職代行」では、自分では言いにくい「辞めさせてほしい」を自分で言わなくても代行して伝えてくれる「退職代行サービス」を提供しています。
退職代行サービスは、会社に行かずに誰とも会わず連絡もせずに退職できるのも大きなメリット。退職手続きについてもサポートしますのでどうしていいかよくわからなくてもお任せいただけます。
「わたしNEXT<女性の退職代行>」「男の退職代行」の退職代行サービスは、退職成功率100%、即日当日退職可能、ご相談無料(LINE、メール、電話)、転職成功への近道である転職サポートも無料でご利用いただけます。
全国対応ですので24時間いつでもご相談ください。
-
前の記事

退職代行で訴えられるリスクはある?損害賠償請求や訴えられない絶対防御とは 2024.05.31
-
次の記事

後払い分割払いOKの退職代行おすすめ2強!お金がない人も即日退職できる 2024.06.10